安寿と厨子王
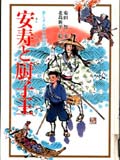 「越後の春日を経て今津へ出る道を、珍しい旅人の一群が歩いている。母は三十歳をこえたばかりの女で、二人の子供を連れている。
姉は十四、弟は十二である。」(森鴎外「山椒大夫」より)
「越後の春日を経て今津へ出る道を、珍しい旅人の一群が歩いている。母は三十歳をこえたばかりの女で、二人の子供を連れている。
姉は十四、弟は十二である。」(森鴎外「山椒大夫」より)
画像出典 : 「安寿と厨子王」 歴史春秋社
菊田智・文 北島新平・絵
◇あらすじ
陰謀によって西国に流された父のために、安寿と厨子王、母、乳母の4人は、京へ旅立つ。越後の直江津にたどり着いた一行は、人買いにだまされ、姉、弟が丹後に、母、乳母は佐渡に売られてしまう。丹後の由良で山椒大夫に買い取られた2人は、つらい労働を強いられる。安寿は厨子王を密かに逃がすが、ひどい拷問にあい、命を落とす。一方厨子王は姉から渡された地蔵菩薩の霊験により身を守られ、無事京都にたどり着く。帝から父の許し状をもらい、国守となった厨子王は、長い苦難の末母と再会する。
◇作品について
この物語は、中世に起こった「語り」の一種で、説経節と呼ばれ、庶民に親しまれてきた。歌経節、説経祭文、説経浄瑠璃など少しずつ形を変えながら、近世に引き継がれ、通俗化していく。江戸時代に入って、人形浄瑠璃や歌舞伎などに取り入れられて、しばしば上演された。数多くの説経節の中で、五大説経のひとつと言われるほど有名である。
明治に入り姿を消した「語り」も、森鴎外が1915(大正)年「山椒大夫」を文学作品として書き表し、広く読まれるようになる。安寿が拷問で死ぬ場面が、この作品では、沼に身を沈める入水として書かれている。

安寿と厨子王の供養塔が、直江津の関川河口近く、琴平神社の境内にある。直江津は、中世海陸交通が盛んになるにつれ、遠国との交通の要路となり、人買いも行われたようである。
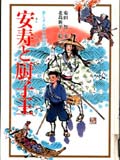 「越後の春日を経て今津へ出る道を、珍しい旅人の一群が歩いている。母は三十歳をこえたばかりの女で、二人の子供を連れている。
姉は十四、弟は十二である。」(森鴎外「山椒大夫」より)
「越後の春日を経て今津へ出る道を、珍しい旅人の一群が歩いている。母は三十歳をこえたばかりの女で、二人の子供を連れている。
姉は十四、弟は十二である。」(森鴎外「山椒大夫」より)