
画像出典 : 『頸城文学紀行』より
小林勉・著 耕文堂書店
 画像出典 : 『頸城文学紀行』より 小林勉・著 耕文堂書店 |
本名 | 小寺佐和子 |
| 出生年 | 昭和5年(1930年) | |
| 出生地 | 新潟県高田市(現在 上越市) |
| 昭和25年(1950年) | 長野女子専門学校、国語科を卒業 |
| 昭和32年(1957年) | 『かくまきの歌』他の短編で日本児童文学者協会新人賞を受賞して文壇に進出した |
| 郷土の先輩「小川未明」を手本として学ぶ | |
| 新潟日報お母さんの童話に入選 | |
| 昭和47年(1972年) | 『小さな雪の町の物語』では小学館文学賞を受賞 |
| 昭和58年(1983年) | 『小さな町の風景』では赤い鳥文学賞を受賞 |
| 『白い道の記憶』で新潟県同人誌連盟賞を受賞 | |
| 日本児童文学者協会会員 |
◎最近出版された本
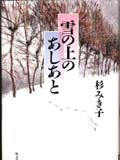

|
|
画像出典 : 『小さな町の風景』 杉みき子・著 佐藤忠良・絵 偕成社 『雪の上のあしあと』 杉みき子・著 村山陽・絵 恒文社 『寺町だより』 杉みき子・著 村山陽・絵 新潟日報事業社 |
| 杉みき子 作 昭和47年(1972年) |
 | |
この本は15の短編からできています。 冬を舞台にした話が、「冬のおとずれ」「きまもり」「走れ老人」「小さな旅」などです。 |
||

| 杉みき子 作 平成13年(2001年) |
| 「三本のマッチ」 | 「えんとつのなかまたち」 | 「子すずめと電線」 |
| 「ふしぎなこと」 | 「おぼろ月夜」 | 「音」 |
| 「空気食堂」 | 「花作りのおじいさん」 | 「おじぞうさまと鬼」 |
| 「あくまの失敗」 | 「あじさい」 | 「百ワットの星」 |
| 「森のそめものや」 | 「くもの電気やさん」 | 「坂みち」 |
| 「雪の一本道」 | 「おばあちゃんの雪見どり」 | 「さんぽするポスト」 |
| 「朝市にきた女の子」 | 「雪のテトラポット」 | 「ばんばら山の大男」 |
| 「やねの上のどうぶつえん」 | 「とび出しちゅうい」 | 「あの子に会う日」 |
| 「あしあと」 | 「十一本めのポプラ」 | 「防風林のできごと」 |
| 「月夜のスキーリフト」 | 「雪道チミばなし」 | 「雪の日のアルバム」 |
| 「長い長いかくれんぼ」 |